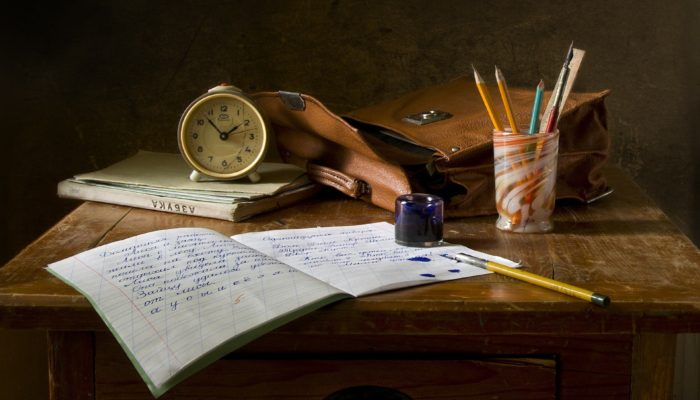
1.遺贈は放棄できる
ある人に遺贈したい。自分の死後に財産を有効に使ってほしい。
遺言書を作成しておけば自分の財産を特定の人に渡したり、渡したい財産をコントロールできます(遺留分の問題はありますが)。
しかし、遺言者の意思とは裏腹に、受遺者が遺産を受け取ってくれるかどうか、は別の問題です。
なぜなら、遺言は遺言者の一方的な意思のみでされるものであり、遺言者と受遺者の契約ではありません。
たとえば、いらない土地、活用できない土地を遺贈されたが、固定資産税や維持・管理費用などの固定費を負いたくないといった場合もあるでしょう。
そのような場合にまで受遺者は絶対的に遺贈を受け入れなければならないとすると、「押し付け」のように感じるでしょう。
では、遺産を受け取りたくない、望まない遺贈は放棄することができるのか。
結論から言うと、遺贈は放棄することができます。が、特定遺贈と包括遺贈で放棄の方法が異なります。
2.特定遺贈の放棄
特定遺贈(※)がされている場合、受遺者は遺言書の効力が発生した後、つまり遺言者の死亡後であれば、いつでもその遺贈を放棄できます。
(※相続財産のうち特定の財産を、指定した人物に遺贈すること)
その方式にも制限はないため、口頭での意思表示でも法律上は有効です。
ただし、トラブル防止のため、証拠を残す意味でも放棄の意思表示は一般的には内容証明郵便(配達証明付き)によってされます。
いついつまでに放棄しなければならない、といった期限もありませんが、いつまで経っても承認するか放棄するかの意思表示がなければ遺言執行者(指定がなければ相続人)は困ってしまいます。
そのため、遺言執行者(相続人)は、受遺者に対して承認するか放棄するかを催告できます。
一定期間を経過しても回答が無ければ遺贈を承認したものとみなされ、遺贈放棄をすることができなくなります。
特定遺贈の一部放棄はできるか?
遺贈の目的物が複数あり、それが分けることのできるものであれば、遺贈の一部放棄をすることも可能です。
放棄の意思表示はだれに対してするか?
遺言者はすでに亡くなっているため、放棄の意思表示を遺言者にすることはできません。
この場合、放棄の意思表示(通知)は、遺言執行者(相続人)に対して行います。
上述のとおり内容証明郵便(配達証明付き)で通知することが将来のトラブル防止につながります。
3.包括遺贈の放棄
特定遺贈の放棄は意思表示で放棄が可能ですが、包括遺贈(※)の放棄は気を付ける必要があります。
(※相続財産の全部または一定の割合(全財産の2分の1、3分の1など)を特定の人物に遺贈すること)
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する、とされています。
「財産を包括的に遺贈されるのであれば、もはや相続人と同視できる」ということです。
相続人とまったく同じ立場となるので、包括受遺者は遺産分割に参加する必要がありますし、借金などの債務も承継します。
もっとも、相続人と同視できない部分もいくつかあるので注意を要します。
そして、相続人と同視されるということは、包括遺贈の放棄は相続放棄と同じルールにしたがう必要がある、ということです。
相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申立てが必要です。
同じルールにしたがう、ということは包括遺贈の放棄も相続開始後3か月内に包括遺贈を承認するか放棄するかを選択することになります。
相続放棄と同様に3か月を経過したり、遺贈されたものを処分したりすると、遺贈を承認したとみなされます。
放棄を選択するならば、家庭裁判所に包括遺贈放棄の申立てをする必要があります。
その方法や添付書面は相続放棄の場合とほぼ同じですが、包括遺贈であることを証明するために「遺言書」の提出が必要になります。
包括遺贈の一部放棄はできるか?
相続放棄と同じルールにしたがうことになるので、相続放棄と同様、包括遺贈の一部放棄は認められません。
たとえば、不動産は放棄するが預金は遺贈を受けるといったことはできません。
これを認めると他の相続人や利害関係人に大きな影響を及ぼし、法律関係が複雑化するからです。
4.負担付遺贈の放棄
遺贈を放棄した場合、その遺贈が「負担付遺贈」であった場合は、負担の受益者が自ら受遺者となります。
どういうことか。
たとえば、「Aに〇〇不動産を譲るが、その代わりに私の妻Wの生活の面倒を終生みること」とする負担付遺贈がされているとします。終生生活の面倒をみること、が負担部分です。
Aが負担を重荷に感じ、その遺贈を放棄したとすると、遺言者の妻Wが当然に受遺者になります。
Wはこの負担付遺贈で利益を受ける者、受益者(※)だからです。
(※負担付遺贈がされると、Wは生活の面倒を終生みてもらうことができ、その点が受益といえます。つまりWは受益者ということです)
Wは、受遺者になる旨の意思表示は必要ではなく、当然に受遺者になります。
受遺者になることを望まないのであれば、遺贈の放棄をする必要があります。
Wは配偶者ですが、仮にWではなくまったくの第三者であったとしても、その第三者は当然に受遺者となります。
ただし、遺言者が遺言で別段の意思表示をしていた場合、たとえば、
「本負担付遺贈が放棄された場合は代わりに次男Bに財産を譲る」
となっていれば、受益者WではなくBへの負担付遺贈となります。
BがWの生活の面倒をみる代わりに遺贈を受けることができます。
5.遺贈を放棄するとどうなる?
遺贈が放棄されると、放棄された部分は法定相続人が相続することになります。
もっとも、その遺言に遺贈が放棄された場合の取り扱いについて書かれていれば、当然その内容に服することになります。
たとえば、「Aが本遺贈を放棄した場合はAの子Bに遺贈する」と書かれている遺言で、Aが遺贈を放棄すれば、遺言どおりBへの遺贈となります。
6.受遺者の立場と相続人の立場は別
包括遺贈を放棄したからといって、相続人としての地位までを放棄したことにはなりませんので、相続人としての地位で相続はできます。
相続人としての地位も放棄したければ包括遺贈の放棄に加えて別途、相続放棄の手続きも必要になります。
逆も同様で、相続放棄をして相続人ではなくなったとしても、包括遺贈の放棄をしていなければ包括受遺者の立場として被相続人の権利義務を承継します。
たとえば、「相続放棄をしたから自分はもう返済義務はない」と債権者に主張したとします。
しかし、債権者から「包括遺贈を受けているではないか」と主張されてしまえば、請求を拒むことはできません。
包括遺贈を放棄したため何も相続するものはないと勘違いし、相続開始から3か月経過した結果、多額の借金を意図せず相続してしまう可能性もあるので注意を要します。
7.遺贈放棄の意思表示を撤回することは?
一度行った遺贈放棄の意思表示を撤回することは原則できません。
例外的に、第三者の詐欺や強迫によって相続放棄がされた場合や、成年被後見人が成年後見人の代理を受けずに相続放棄をした場合は、放棄の取り消し、撤回が認められます。
この点は相続放棄と同じ考え方です。
詳しくは<やっぱりやめたい!相続放棄の撤回、取消しはできる?>
8.まとめ
以上のとおり遺贈の放棄は、特定遺贈か包括遺贈かで方法が異なります。
特に、包括遺贈の放棄は相続放棄と同じように3か月の期限があります。
遺贈の対象物を処分してしまうと単純承認となるので、遺贈の放棄を検討しているのであれば財産を処分しないよう、注意を要します。
遺贈は受遺者の意思に関係なく、遺言者の一方的な行為によってされます。
そこには受け取りたくない財産が含まれている可能性もありますし、受けたくない事情があるかもしれません。
「遺贈は放棄ができる」ということを知っておくだけでも有用でしょう。


