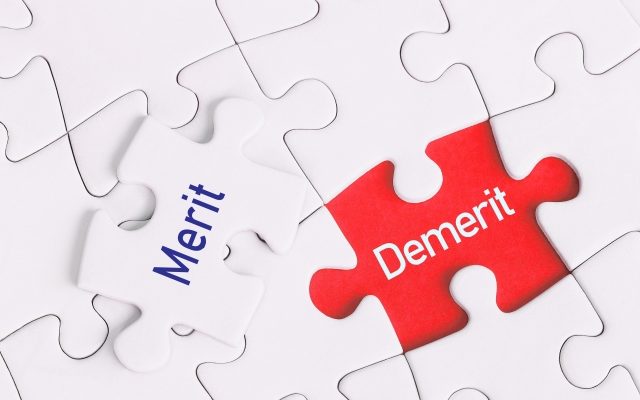
1.成年後見人にはだれがなっている?
「不動産を売却したいけど判断能力、意思能力がないため売買契約を結ぶことができない」
「遺産分割協議を行いたいが、認知症で協議ができない」
など、本人が意思能力、判断能力を欠く状況になった場合に、それらの行為をするには、その本人に代わって意思表示を行う法定代理人、「成年後見人」を選任する必要があります。
この成年後見人制度ですが、成年後見人を必要としている方と、実際に成年後見制度を利用している方の数には大きな開きがあります。
成年後見制度の利用件数は、2000年4月1日の制度発足から2019年時点で累計が22万件ほどですが、潜在的なニーズ、つまり後見人を必要としている人の数は約1000万人といわれています(今後も高齢社会の影響で、潜在的ニーズは増加の一途をたどることが予想されます)。
わずか2%の方にしか成年後見人が選任されていない。
残り98%の方は、自ら適切に財産管理を行うことが不十分、もしくは困難な状況であるにもかかわらず、法律上の後ろ盾をもってサポートしてくれる人がいないのです。
親族が法的枠組みの範囲外で親族の立場、ということで事実上サポートだったり、契約だったりを行っているのが現状です。
では、成年後見人を利用した。
成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、親族が成年後見人に選任される割合は3割に満たない、といわれています。
残りの7割以上は司法書士をはじめとした専門家が選任されています(なお、制度発足当初は親族の方がより多く選任されていました)。
現在は専門家が成年後見人に多く選任されているところですが、いずれにしてもまったくと言っていいほど成年後見のニーズ、潜在需要を満たしていない状況です。
ただ、一気に利用者が増えると、そのすべてを専門職でカバーできるはずはないため、当然担い手が不足してしまいます。
そのため、今後、後見制度に親族がより一層関与してくることが求められますし、そのような状況が想定されます。
以下では、親族が成年後見人になった場合のメリット・デメリットを解説します。
2.親族を成年後見人にした場合のメリット
子や兄弟姉妹などの近しい親族が成年後見人になった場合のメリットです。
本人にストレス、負担を与えない
親族以外の第三者が成年後見人に選任することは、少なからず本人にストレスを与える場合があります。
親族であれば、余計なストレスを与えることもないでしょう。
本人のことをよく知っている
親族であれば本人の性格や人となりなどを含め、本人のことをよく知っているのではないでしょうか。
この点、専門家が成年後見人になった場合には、その時点では本人はすでに認知症などで判断能力を欠いていることが多いため、本人とうまく意思疎通ができない場合があります。
スムーズに職務に移れる
身近な親族であれば成年後見人になる前から事実上、財産管理などをしていることが多いでしょう。
本人のいまの状態やだいたいの資産状況を把握しているため、スムーズに成年後見業務(財産管理、身上監護)を行うことができます。
近くに居住していることが多い
本人と同居している場合もありますが、本人が施設や病院に入っているなどで同居していなくても、比較的近くに住んでいることが多いです。
そのため、急な事態にも迅速に対応ができますし、定期的な訪問や面会も気軽にできます。
報酬がかからない場合もある
専門家が成年後見人になると、必ず報酬が発生します。
この報酬額ですが、職務の難易度や大変さ、本人の収支状況、資産規模などを総合的に考慮して家庭裁判所が金額を決定します。
一般的には月々2万円から4万円ほどです。
一方で、親族が成年後見人になった場合は、無報酬で行うことも珍しくありません。
同居の親族、近しい親族であればあるほど無報酬で行っていることの方が多いのではないでしょうか。
それらの者は、基本的に成年後見人に選任される前から事実上、後見職務に相当することを行ってきた。
そのため、「報酬を請求する」といった感覚がそもそも芽生えず、また、本人が亡くなると結局は自分が相続人になる場合が多いため、わざわざ家庭裁判所に対して報酬請求をしないのです。
なお、親族が報酬を請求しても何ら問題はありませんので、報酬を欲しいと考えているのであれば、年に1度、報酬付与審判の申立てを行う必要があります(1年間の報酬が決定し、その金額を本人の口座から引き出して報酬に充てることになります)。
医療同意に対応可能
成年後見人には、医療同意権がありません。
ただ、親族が成年後見人になっているのであれば、親族の立場として、医療同意に関与することが可能です(実務上もそのような対応がされています)。
これが、まったくの第三者である専門職後見人では難しいでしょう。
3.親族を成年後見人にした場合のデメリット
メリットがあればデメリットもあります。
職務が煩雑なので負担が大きい
成年後見人の職務は、財産管理と身上監護です。
まず本人の収支を管理する必要があります。
一定金額以上の支払いを行った場合には領収証の保管が必要になりますし、本人に代わって施設入所契約や売買契約などの法律行為、本人と定期的な面会なども必要になってきます。
また、基本的に年1回、家庭裁判所に事務報告をする必要があります。
親族はこれらの事務に慣れていないことでしょうから、負担やプレッシャーを感じるのではないでしょうか。
他の相続人との関係性
親族が相続人でもある場合は、他の相続人との関係性によってはトラブルにつながるおそれもあります。
相続人でもある成年後見人が、通帳や現金を管理していることに不満を持つ他の相続人がいないとも限らないからです。
実際に、他の親族から、
「親の通帳から勝手に引き出して私腹を肥やしているのではないか」
「財産を囲っているのではないか」
とあらぬ疑いをかけられた親族後見人の方もいました。
無意識のうちに財産を本人以外のために使っている
成年後見人は、本人の財産は本人のためにしか使うことができません。
しかし、親族が成年後見人になっている場合では、本人以外のために財産を使っているケースがみられます。
悪意なく本人の財産を使っているとしても、知らず知らずのうちに自己や家族のために使っていた場合もあります(家族のために使ったとしても、それが扶養義務の範囲内であればまったく問題はありません)。
「本人の財産は本人のためにしか使えない」
これが成年後見制度の大原則です。家族信託のような柔軟性はありません。
親族後見人の場合、専門職後見人と比べて、そのような意識がどうしても薄いことが挙げられます。
4.まとめ
親族が成年後見人に選任された場合のメリット・デメリットを解説しました。
成年後見人、親族の割合が少ないのが現状ですし、親族を後見人候補者として申立てしても、必ずしもその者が選任されるとは限りません。
専門家が成年後見人についている割合の方が、圧倒的に多いです。
親族、専門家、どちらがよいのか。
成年後見人に最適なのかどうか、どちらがよいのか、は本人との関係や本人の収支状況、資産状況、他の相続人との関係性など、様々な要因が絡んできます。
まずは親族後見のメリット・デメリットを見極めることも大切になってきます。


