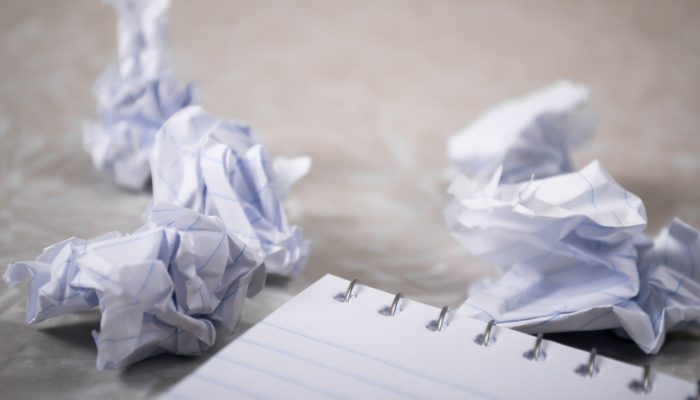
1.遺言書に書いた財産内容に変動があったら
遺言書は、遺言を書いた遺言者が亡くなることにより効力が発生します。
そのため、作成から効力が発生するまで数年、場合によっては数十年が経つこともあります。
その間に、遺言書に書いた財産に変動、変化が生じることもあるでしょう。
そのため、作成当初に遺言者が思い描いていた内容と違う結果となってしまわないように注意する必要があります。
以下は、遺言書作成後、遺言の効力が発生するまでに不動産と金融資産に変動、変化があった場合の対処方法です。
不動産が変動した場合
たとえば、妻に土地建物を相続させる旨の遺言を書いているとします。
しかし、遺言を書いた後に建物を建て替えた場合。
書いた当時はその建物(新建物)は存在しません。
そして、遺言の効力が発生した時点では書いた当時にあった建物(旧建物)も存在しません。
これでは、旧建物はもちろん、新建物についても妻に相続させることができなくなり、遺言ではなく法定相続になってしまいます。
そのような場合。
まずは遺言書を書き換えることにより不測の事態を回避できます。
手間はかかりますが、あらためて新建物を記載した遺言書を作成することも選択肢に入れるべきでしょう。
旧建物と、新建物の立っている場所は同じだとしても、登記簿の記載はまったく一致しません。
当然、床面積は違ってくるでしょうし、場合によっては家屋番号(建物を特定するための番号)も違ってきます。
あらためて遺言書を書き換えることにより、新建物について登記簿どおりに記載し、正確に特定することができます。
もう1つ、遺言書の書き方を工夫する方法があります。
最初の遺言書を書いた際に、将来、建物を建替えた場合のことを念頭に置いて、その旨を一言加えておくことのです。
たとえば、
「妻にA土地、B建物を相続させる、ただし、同建物を取り壊し、A土地上にあらたに建物を新築した場合は、その新築建物を相続させる」
としておく。
もしくは、シンプルに、
「遺言者の相続開始時に有する全財産を相続させる」
とする遺言にしておく。
ただし、遺言執行の点からみると正確に財産を明記しておく方が好ましいですし、このような包括的な記載をよく思わない公証人もいます。
金融資産が変動した場合
不動産以上に変動が予想されるものとして、預貯金や株式などの金融資産があります(この変動とは、預金残高や株価の変動ではありません。それらの額は必ず変動するものですし、そもそも遺言書には預金残高や株価は記載しません)。
たとえば、遺言書作成時には、妻にA銀行〇〇支店の預金を相続させる旨の内容であったとします。
その後、同口座を解約しB銀行◇◇支店に乗り換えた場合(乗り換え理由は金利が高い、家から近い、管理しやすいなど様々でしょう)。
遺言者としては、そのままB銀行の口座預金も妻に相続してほしいと考えていたとしても、当初作成した遺言書には「B銀行の預金を相続させる」と書かれていないので、そのままではB銀行の口座預金は法定相続となってしまいます。
遺言で妻に渡すことができません。
したがって、金融資産についても、もしもの場合に備え、前述の不動産の場合と同様にあらためて遺言書を書きかえるか、書き方を工夫する必要があります。
2.まとめ
遺言書の効力が生じるまで普通、一定期間を要します。
その間に遺言書に書いた財産の内容が変動することもあるでしょう。
当初作成した遺言書の内容ではうまく対応できないケースも出てきます。
このような不都合が生じないよう、遺言書を作った後には定期的に内容を見直すことをオススメします。
相続人や遺産の変化など、実情に沿った内容になっているかどうかを確認することが重要です。
作成当初から財産の変動が見込まれるのであれば、様々なケースに対応できるように工夫して書くことが将来の負担軽減につながることでしょう。
ただ、工夫をしてみたが、それによって遺言の内容が不明瞭になったり、記載ミスにより相続させたい人が取得できない、といった事態になれば大変です。
遺言は自分が死んだあとの話です。
取り返しのつかないことにならないよう、具体的な記載の仕方について分からない点があれば専門家に相談することをオススメします。


