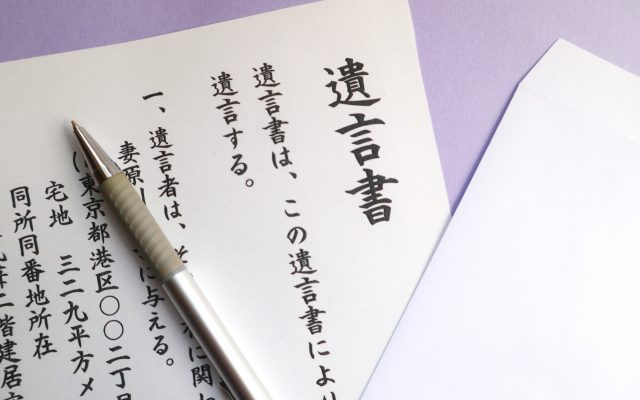
遺言書は被相続人の最終意思を実現するものです。遺言書に間違いやミスがあってはなりません。
しかし、自筆証書遺言は専門家の関与なく作成されていることが少なくないため、誤記や記載ミスが散見されます。
場合によっては、遺言書が無効となってしまう可能性もあるので、注意を要します。以下では、遺言が無効となってしまったことにより、大変な事態となったケースをご紹介します。
1.遺言が無効?
ある方が遺言書を作成していました。
その方には子がおらず、両親もすでに亡くなっているため、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹です。
遺言書の内容は、配偶者に全財産を相続させる、とする自筆遺言書を書いていました。
兄弟姉妹は遺留分がないため、そのような遺言内容であっても、配偶者が全財産を完全に取得できます。
遺留分侵害額請求をされるおそれがありません。
遺言書を残し、まずは一安心でした。
しばらくして、その方は亡くなりました。
その遺言書を使って名義変更など各種相続手続きをお願いしたいということで、配偶者の方が遺言書を持って、ご相談に来ました。
遺言書を確認してみると、なんと、日付が「平成〇年〇月吉日」となっていました。
自筆遺言書の要件は厳しいため、正確に作成日付が書かれていないと遺言書が無効となってしまいます。特に自筆遺言書において作成日付は重要な部分です。
当然、「吉日」は具体的な日付が特定できず、認められないため、無効です。
その遺言書は日付のない遺言書として無効となり、これでは手続きができません。
つまり、遺言がないものとして法定相続のルールにしたがうことになります。
その配偶者の方には、
「残念ながら遺言が無効なので他の相続人である兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がある」
「そして、全員の実印と印鑑証明書も必要になる」
ことをお伝えしました。
2.相続人が30人?
被相続人には不動産や預貯金もありましたので、それらの手続きを行うにはどうしても他の相続人の関与が必要になってきます。このまま放置することもできません。
そこで、まずは相続人を調査する必要があるため、調査したところ、被相続人には数人の兄弟姉妹がいました。
また、親には離婚歴があり、前妻との間に子が数人いました(前妻の子も異母兄弟なので、相続人となります)。
さらに、兄弟姉妹の中にはすでに亡くなっている方もいましたので、代襲相続が発生し、その子(被相続人からみると甥姪)も相続人となります。
戸籍収集だけでも相当の時間と手間がかかりましたが、収集、調査の結果、相続人は30人あまりとなりました。
もちろん、その30人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
「知らない、会ったこともない」
「付き合いがないからいいのではないか」
などは通用しません。
まず、相続人全員に相続関係図などの資料とともに事情を書いた手紙(経緯やどのような方針であるか)をご説明し、回答書を同封のうえお送りしました。
回答書の結果、全員からご協力いただけることとなり、追って、配偶者の方が相続する内容の遺産分割協議書を各相続人に送りました(ハンコ代として商品券は必要になりましたが)。
結局、1年近くかかりましたが、相続人全員の実印と印鑑証明書を取得でき、不動産の名義変更をはじめとした相続手続きをすべて行うことができました。
3.まとめ
以上のとおり遺言書が無効となってしまうと、法定相続となります。
その結果、大変なことになってしまう場合があります。
遺言が無効となってしまい、想定外の事態にならないよう、自筆証書遺言を書いた場合は、一度、専門家に確認、チェックしてもらうことをオススメします。


