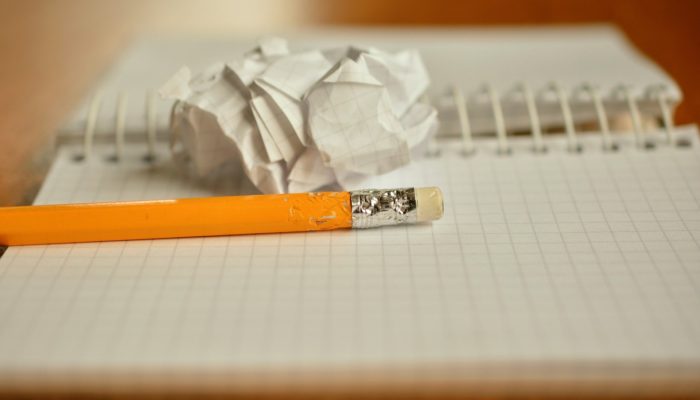
自筆遺言書はいつでも、どこでも、費用をかけることなく作成できますが、専門家が関与せず作成されていることが多いです。
そのため、民法の要式を満たしていないとして遺言書自体が無効となる場合ももちろんありますが、中には要式は満たしているため無効とはならないが、記載内容がマズい遺言書に出くわすことがあります。
むしろ、自筆証書遺言においては疑問の余地を挟むことがない、完璧に書かれている遺言書に出くわす方が少ないように感じます。
特に頭を悩ませるのが、以下のような「マズい」ケースです。
1.相続財産を与えるための文言、表現のマズさ
だれかに相続財産を遺言で与える場合、一般的には「相続させる」「遺贈する」といった表現になります。
しかし、中にはマズい表現を使っているケースがあります。
たとえば、〇〇〇に遺産を「託す」「任せる」「ゆだねる」などの表現を使っているケースです。
このような表現は、何かをあげる、渡すときに使う表現ではないです。
遺言者自身の意図、考えとしては「相続させる」「遺贈する」「譲る」「与える」「取得させる」ことであったとしても、第三者が見て、「託す」などといった表現をどう思うか、判断するかです。
つまり、「託す」や「任せる」などの表現方法では単に託すだけなのか、管理させるだけの趣旨なのか、または相続により取得させたいのかどうかの判別がいまいちつきません。
したがって、このような曖昧な表現では相続登記をはじめとした遺言執行ができない可能性があります。
また、その曖昧な表現がどのような意図なのかを巡って、相続人間で紛争に発展する可能性もありますので、曖昧な表現は避けることです。
2.相続財産の特定のマズさ
遺言において相続財産の特定が重要なのは言うまでもありません。
「全財産を相続させる」や「全財産の2分の1を相続させる」と書く場合には特に問題になることはありませんが、全財産ではなく、具体的に財産を特定する場合に問題となることがあります。
特定が不正確だと、実際に遺言執行するにあたってスムーズにいかないことが多々あるからです。
以下は、代表的な財産として不動産と預貯金を遺言で特定する際の留意点です。
不動産の場合
不動産を遺言で相続させたい、遺贈したい場合、遺言書に書く際には、必ず、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本のこと)どおりに書くことです。
登記事項証明書が古いもの、だいぶ前に発行されたものであれば、最新のものを取得しておくことをオススメします。
よくあるマズいケースとしては、自分の住所で自宅不動産を特定してしまうことです。
なぜなら、当然に自分の住所がそのまま自宅不動産の所在とはならないからです(ただし、地方などは住所が不動産の所在とイコールの場合もよくあります)。
たとえば、「〇〇市〇〇町1丁目2番3号の土地建物を相続させる」と書いている遺言は、明確に土地建物を特定しているとは言えません。
〇〇市〇〇町1丁目2番3号はあくまで住居表示、いわゆる住所であり、不動産の所在ではありません。
不動産登記事項証明書上の不動産の所在は、全然違う「〇〇市〇〇町3番9」などとなっていることもあるのです。
勘違いしやすいところですが、不動産を特定するための所在、地番や家屋番号と、住居表示としての住所は別になります。
実務上でも遺言書に書いている不動産の表示と、実際に相続させたい不動産の表示が一致していない遺言書が散見されます。
これでは内容に疑義が生じ、無用の混乱を招く可能性があります。
もっとも、法務局としては遺言書全体の記載からみて、遺言書に書かれている不動産の表記が登記簿とは異なっていても、実際はその登記簿の不動産を指していると評価、判断してくれれば、登記を受け付けてくれるはずです。
しかし、それでも絶対とは言いきれませんので(法務局によって判断に差が出る)、やはり正確に書いておくことです。
場合によっては、相続人全員の上申書(印鑑証明書つき)が必要となることもあります。
預貯金の場合
預貯金を特定する場合は銀行名だけを書かずに、その支店名や口座番号、預金種別も正確に書いておく必要がありますが、預金残高を書く必要はありません。
通帳を見ながら記載ミスのないよう書きましょう。
「あの不動産を渡す」「あの銀行預金を預ける」などの表現はマズい遺言書の代表のようなものですので気を付けましょう。
なお、改正相続法により、財産目録を「添付」する方法によれば財産については自書する必要がなくなったため、相続財産の記載ミスやマズい表現を回避、予防することができます。
詳しくは<財産目録はパソコンで作成してもよい?自筆証書遺言の要式緩和>
3.相続財産が漏れているマズさ
相続させたい財産が漏れる可能性もあります。
不動産の場合は権利書の確認が必須です。
ちゃんと登記事項証明書どおりに土地建物を書いていても、不動産の一部、たとえば道路持分を漏らしている遺言書がまれにあるからです(自宅については把握しているが道路持分は知らない、といった方は案外多いです)。
権利書が手元にない場合は、登記事項証明書を共同担保目録付きで取得することです。
通常、自宅には銀行から借りた住宅ローンの担保として抵当権が設定登記されています。
そして、登記事項証明書の共同担保目録という部分を見れば、担保に取っている物件がすべて記載されます。
銀行などは道路持分も担保に取っていますので、共同担保目録に道路持分の土地の記載があれば、そこで、道路持分の存在が分かります。
遺言書を書く際には共同担保目録付きの登記事項証明書で確認しながら記載することです。
記載漏れの物件については原則どおり法定相続分で各相続人が相続することになりますので、別途、相続人全員の遺産分割が必要になってしまいます。
道路持分だけを遺産分割協議することにもなりかねないので、注意しましょう。
同じく忘れやすいのが、定期預金の存在です。
普通預金については遺言に書いていても定期預金を書き忘れると、当然、定期預金は遺言の対象とはなりません。
各相続人に法定相続分で相続され、場合によっては遺産分割をするハメになってしまいます。
4.まとめ
自筆証書遺言は気軽に作成できるため、多く利用されているところですが、記載内容がマズくてときには相続人や専門家を悩ませます。
争続に発展するおそれもありますし、最悪、その遺言では手続きができない、といった場合もあります。
自分の最終意思を実現させるためにせっかく書いた遺言書なのに、そのような結果となってしまうことは大変残念なことです。
書き方に迷った、書き方が分からない、といったことであれば専門家に相談するか、もしくは費用や手間はかかりますが、公正証書遺言の作成をオススメします。


