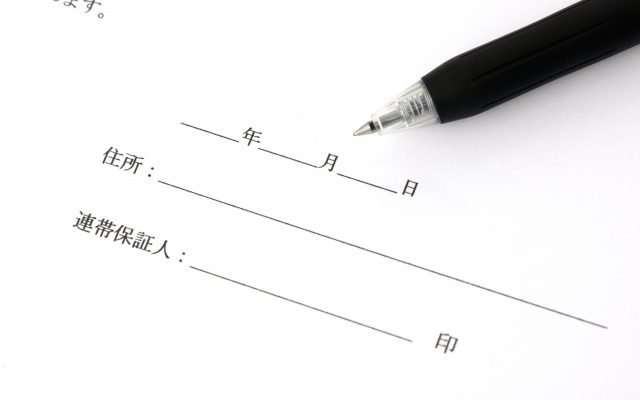
1.保証債務の相続
被相続人が会社を経営していた場合、生前に会社の借入の連帯保証人(※)として個人保証をしていることがよくあります。
(※連帯保証人は実際に借入した債務者と同等の責任を負います)
また、知人の借金の連帯保証人となっていることも。
相続が開始すると、相続人は被相続人自身が背負った借金と同じように、その連帯保証人としての地位、責任を相続します。
保証人となっている事実を何も知らされていない場合であっても、「当然に」だれかの借金の肩代わりをする債務、義務を相続します。
通常、他人の借金を肩代わりした事実を家族には隠したいものです。
そのため、被相続人が保証人になっていた事実を相続人がまったく知らないといったことは珍しくありません。
債務者がちゃんと返済してくれればよいですが、後々、実際に借金した債務者が支払えず、返済の請求がきたときにはじめて知った、ということは珍しくはありません。
「自分は知らないから関係ない」「親が勝手にやったことだ」は通用しません。
2.返済義務は法定相続分で負う
保証債務を相続した場合、相続人は実際にどれくらいの割合で支払う必要があるのでしょうか。
たとえば、相続人が配偶者と長男、次男の3名とします。
被相続人が他人の600万円の借金の保証債務を負っていたなかで死亡し、債務者が返済できない状況となったとします。
債権者から、相続人に対して保証債務の履行請求がきた場合は以下の金額を限度として支払い義務が発生します。
・配偶者(法定相続分2分の1)・・・300万円
・長 男(法定相続分4分の1)・・・150万円
・次 男(法定相続分4分の1)・・・150万円
仮に、遺産分割協議で保証債務を長男のみが負うと合意しても、それはあくまで相続人の内部的な取り決めであり、法的には効力はありません。
つまり、「遺産分割の結果、保証債務を長男が相続したから長男に請求してくれ」と債権者に主張することはできません。
特定の相続人のみが負担すると合意しても債権者は法定相続分に応じた金額を請求できます。
ただし、債権者側から遺産分割の合意内容にしたがうことは問題ありません。
3.保証人の地位を相続した場合の対処法
保証債務を相続し、相続放棄も選択肢にないのであれば、債権者とうまく交渉するしかありません。
可能性はそれほど高くはないですが、場合によっては猶予や減額に応じてくれるかもしれません(任意整理)。
債権者との交渉もうまくいかず、相続放棄もしないとなると、取り得る方法としては以下の3つがあります。
①民事調停
裁判所で調停委員を交えて、返済方法などについて話し合います。
②破産
保証債務を履行できなければ、破産手続きを行うことも選択肢になります。
③個人再生
破産をしてしまうと、家も手放さなければなりません。
それはどうしても避けたいのであれば、個人再生を選択します。
住宅ローンを返済しながら(家を所有したまま)、保証債務を一定額まで圧縮できます。
4.保証人が代わりに支払ったら
債務者の代わりに保証人が債務の返済をすると、保証人は債務者に「求償権」を行使できます。
この求償権とは、簡単に言うと肩代わりした分を債務者本人に請求する権利です。
返済できなかった債務者に対し「保証人である私があなたの代わりに支払ったのだから支払った分を私に返してください」と求めることができるのです。
求償権は、代わりに返済すれば当然に取得し、行使できます。
5.保証債務は債務控除できるか
相続税の課税対象となる遺産総額は、自宅や預貯金現金などのプラスの財産から被相続人の債務や葬式費用などのマイナスの財産を控除して算出します。
そこで、債務の一種である保証債務は債務控除できるのでしょうか。
この場合、保証債務は実際に債務者が返済不能となるまでは具体化しない、不確定なものであるため、また、債務者に対し求償権を行使できることから、原則は債務控除できません。
ただし、以下の状況であれば例外的に債務控除できます。
◆主債務者が返済不能の状態となっている
◆求償権を行使しても返済を受ける見込みがない
6.保証人の地位を相続しない方法
保証債務を相続したくない場合は、相続放棄をするしか方法はありません。
相続放棄は相続開始後3か月内の期限がありますが、保証債務の請求は相続開始後3か月を過ぎてくることもあります。
ただ、期限を経過していても、相続放棄が認められる可能性はあります。
注意点としては、その間に相続財産を処分してしまうと相続の単純承認となり、基本的に相続放棄できなくなります。
相続放棄をすると自宅や預貯金などプラスの財産も相続できません。
なお、勘違いしやすいところとして、相続人自身が被相続人の保証人となっていた場合、相続放棄をしても保証債務は負ったままです。
詳しくは<相続放棄すれば大丈夫?相続人が負っている保証債務と相続放棄の関係>
7.まとめ
以上のとおり、実際に被相続人が負っていた借金に限らず、他人の保証人としての地位も相続します。
保証債務はその存在が判明しにくいです。
債務者が返済している間は請求されません。
今、現実に請求されているわけではないため、あまり自覚がないまま、保証人となっていることを忘れたまま亡くなる方もいます。
しかし、自分が死亡した後、相続人に対して保証債務の請求がいく可能性があることを忘れないようにする必要があります。
遺された家族は何も知らないのです。
そのため、生きているうちに保証債務を負っていることを相続人に直接伝えることです。
それが難しいのであれば、少なくともエンディングノートなどを活用し、間接的に保証人となっていることを知らせるべきでしょう。


