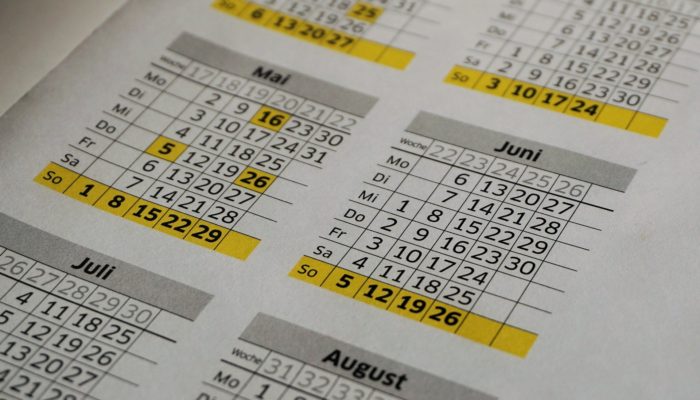
1.いつから10か月?
よく、相続税の申告期限は死亡してから10か月以内、といいますが、その申告、正確には「相続発生を知った日の翌日から」10か月以内に行う必要があります。
たとえば、死亡日が2月1日で死亡を知った日が2月5日であれば、申告期限はその翌日の2月6日からスタートして、その10か月後の12月5日がリミットになります。
ちなみに、申告期限日が土日祝日で休みの場合は、その翌日が申告期限となります。
その翌日も休みならさらにその翌日、つまり翌日以降の営業日が申告期限になります(12月5日が土曜日であれば、12月7日の月曜日が期限)。
2.知った日が相続人ごとで異なると?
この申告期限、相続発生を知った日が各相続人で異なれば、相続人ごとに進行しますので、「申告期限が相続人ごとにバラバラ」となるケースもあります。
そうは言っても、相続人ごとに厳密に知った日の翌日からスタートとすると、各相続人の申告期限が異なることになり、複雑化します。
一方で、昔ならいざ知らず、現在は死亡の事実はその日のうちに知ることが一般的です。
そのため、基本的に死亡日からカウントがはじまることになります。
もっとも、死亡日に相続開始を知ることができなかった特別な事情があれば、当然、知った日からカウントがはじまります。
その場合は、どうして実際の死亡日とは別の日に死亡の事実を知ったのか、を税務署に納得してもらえるような説明ができなければなりません。
3.期限の延長はできる?
申告期限の延長は以下のようなやむを得ない事情があれば、税務署に申請することにより2か月間まで申告期限を延長することができます。
以下の事情があれば自動的に延長されるというわけではなく、税務署に申請して認められた場合に限られます。
胎児が生まれた場合
胎児が生まれてくるまで相続人が確定していないような場合です。
遺言書が出てきた場合
たとえば、相続人以外の第三者に遺贈している遺言書が出てきた場合です。
各相続人の取得額、納付額が変わってくるため、再計算して税の算出をやり直す必要が出てきます。
相続人に異動があった場合
認知や相続人廃除、相続欠格などで相続人に異動があった場合は、基礎控除額や法定相続分も異なってくるため、はじめから税額の計算をやり直して納付額などを算出する必要が出てきます。
4.10か月内に遺産分割が終わっていない場合は?
遺産分割が終わっていないとしても、それだけを理由に申告期限が延長されることはありません。
やむを得ない事情とはいえないからです。
この場合、法定相続分にしたがって申告、納付しておく必要があります。
なお、小規模宅地等の特例や配偶者税額軽減の適用を受けたい場合には申告書とともに「3年内の分割見込書」の提出は必須です。
5.とりあえず期限内に申告、納税はする
期限延長が認められるケースは限定的です。
「仕事が忙しかった」「相続人が病気だった」などの理由では認められません。
1日でも遅れてしまうと延滞税などがかかってくるため、とりあえず申告、納税は申告期限内にしておくことです。
遺産分割を終えていない場合であっても、前述のとおり、法定相続分で分割したものとして申告することになりますが、その際にはくれぐれも「3年内の分割見込書」の提出を忘れないことです。
6.まとめ
相続税の申告期限は相続開始から10か月ではなく、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
その知った日は相続人ごとに判断されますので、相続人によって申告期限が異なるといったことが起こりえます。
もっとも、普通は余裕を持って申告するはずであり、また、基本的に「死亡日」を相続開始を知った日と捉えるため、何らかの影響があるといったケースは少ないでしょう。
この申告期限、やむを得ない事情があれば2か月の範囲内で延長することが認められていますが、認められるケースは限定的です。
基本的には「申告期限は10か月」として認識しておきましょう。
相続税のかかるような場合(もしくは相続税がかからなくても相続税の各種特例を使うような場合)であれば、早めの申告、対応を行うことです。
なお、現在、新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限までに申告できない場合の期限延長の措置が取られています。詳しくは<国税庁ホームページ>


